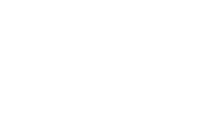![]()
企画女優。
第9回
老グルーピーとみゆきの精神の中の闇の深さ
労グルーピーと美由紀の精神の中の闇の深さ
風俗で働き始めたみゆきの将来に何か展望があったわけではない。ただ生きているだけという現実を受け入れた女の長い長い人生は決して充実という言葉に触れなかった。
一月分の借金15万円也を依頼されたぼくだったが、女に金を貸して戻ってきたためしがなかったぼくがみゆきにそんな金を貸すわけがなかった。
とはいえ、みゆきの困窮した生活も相当なもので、なんのことはないこの金がないとアパートを追い出されるというところまで困っていたのであった。
「実家に帰ればいいじゃん」
「とっくに勘当されてて、親なんか高校生の頃から私のこと見捨ててるよ」
中学生の頃から外人タレントに夢中になり、何度も外泊を重ね、高校も途中でやめて家によりつかなくなっていたみゆきに両親はとっくに愛想をつかしていたようである。まあ、それでも最初の頃は母親が小遣いぐらいはめぐんでいたようなのだが、いずれその金も外人とのセックスのために使われるとわかっては勘当されるのも時間の問題。
結局、ぼくとしてはみゆきがどこかで借金できるまで自分のマンションに泊めてやるしかなかったわけである。
みゆきは「衣装」あるいは彼女たち言うところの「戦闘服」を大量にダンボール箱に詰め込んで、ぼくの部屋に転がりこできた。あっ、それからもっとも大切な「ハメ撮り」写真もいっしょに。
むこうもこちらとやる気はないし、こちらもやる気はなかったので、いっしよに住みながらも肉体関係はないまま3日が過ぎた。そして、みゆきは五反田にあるヘルスに働き場所を見つけて、その寮に引っ越していった。
というのが、みゆきとの思い出のすべてである。そして、今、彼女はビデオ現場でコップいっぱいの小便を前に困りはてていたわけであるが、なんとか飲み干して撮影も一段落。すべての撮影が終了した後、いつものように打ち上げということになったわけである。
当然、話は知り合った頃の思い出話になる。あれからどれぐらいになるのだろうか。5、6年の歳月が流れていて、みゆきも30歳になっていた。グルーピー活動はすでにしていないというので、つまり、「グルーピーをあがった」わけである。あの頃取材先のホテルで顔はとっくにおばさんになっているのに、白塗りのような厚化粧に超ミニでロビーにたたずんでいた「あがれない」老グルーピーの姿を見て、何か得体の知れない気持ち悪さをおぼえたものであったが、その意味ではみゆきはあがったのである。
しかし、あがったにもかかわらず、みゆきからは老グルーピーたちが発しているのと同じ種類の気持ち悪さが漂っていた。
それは一口で言うといかがわしさであった。
ぼくのマンションを出た後、みゆきの生活は完全に根無し草なものになっていく。風俗嬢と言っても、日本人の男をバカにしたようなところのあるみゆきに人気が出るわけもなく、見た目の(肉体)のゴージャスさにもかかわらずまったく指名の伸びないみゆきは店を転々とする。このあたりですでに彼女は典型的な宿無し風俗嬢のパターンを踏襲しているわけだが、仲間のうちで最後まで連絡を取り合っていたピンサロ嬢になったかおりが原因不明の病気で死んだ後は、友達もいなくなって、かおりの生活はまさに「目の前に単に時間が流れているだけ」というものになっていた。
「その時はかおりはエイズで死んだと思ってたのよ。あれだけ不良外人とナマでやりまくっていたら、エイズになってもおかしくないじゃん」
会うたびに痩せているかおり。いつも微熱気味で、元気もなく、みゆきにも病気のことを話さないまま、いつしか連絡がつかなくなって、最後に風の噂で死んだ、というかおりである。みゆきの中にエイズという言葉が浮かんで、自分にも死というものが現実的なものとして忍び寄っているかもしれないと考えたとしてもぜんぜんおかしな話ではない。
実際にかおりがエイズだったのかどうかは誰も知るところではない。ただ、ここではみゆきの中におけるエイズのリアリティーを想像してもらいたいのだが、たとえば、ぼくが同じ立場だったらと思う。
そうしたら、きっと心配で心配で、病院に駆け込んで、エイズ検査をして、結果が出るまで悶々としていただろうと思うのだ。
なのに、毎日が単調に時間が流れていくだけの女にとって、エイズもまたどこか遠い他人の現実のようなものなのだろうか。みゆきは淡々とそんな現実といっしょに生きていた。
そして、ヘルスに勤めることもいよいよ限界になってきた時、みゆきの生活のための選択肢に入ってきたのが、SMクラブである。その頃みゆきもずいぶんやつれ始めていて、もともとボリュームたっぷりだった体も疲れ果てた貧相なものになっていた。みゆき自身は女王様で働きたかったのだが、店の責任者の返事はM女でならというものだった。
そして、たまたまその店がモデルプロダクションをしていたという縁で、みゆきはこうしてAV女優として仕事を始めていたのであった。
しかし、とにかく、SMクラブが経営しているモデル事務所である。在籍している仲間たちも変態やら淫乱やら単なるおかしいのまで含めると、まさに、業界怪奇屋敷。その頃、変態物の受注がたくさんあったAV業界ではなかなか重宝なプロダクションとしてみゆきの事務所はありがたがられていたのであるが、ここのモデル・プロフィールのカードがすごい。
スカトロOK、SMもOKから飲尿、食糞まで、なんでそんな人間がこんなに集まっているんだ! という強烈なインパクトであった。
で、みゆきのカードにはスカトロOK、食糞もOKと書いてあって、それで今回の現場に呼ばれてきたというわけだが、彼女本人がマニアでないことは現場ですぐにわかっていた。
「どうしてプロフィールにこんなこと書いてあるの?」
「同じ事務所に嫌いな子がいて、その子が食糞OKなのよ。だから、私も現場に行ったら
できるかなと思ってスカトロOKにしたんだけど」
というみゆきの返事。要するに、ライバル心だ!
なんという奇妙なライバル心。そういえば、と思い出す。グルーピーたちの外タレに対するハードなアタックはひたすらライバルたちよりも大物を食ったの一点がよりどころであった。
なんと人生の抜け殻のようなみゆきであるが、こんなところに彼女の人生の核がまだ残っていたのである。しかし、結局のところ相手の存在を前提にしたような人生の動機付けに何か意味があるわけではない。
話ついでなので、今まで出会った数々のスカトロ・モデルや変態系のモデルたちのことを思い出してみる。たいていはこういう女の子たちはもともと心に問題を抱えている子たちである。言い方を変えると、バランスのよくない女の子たちというか、たとえば、今まで会った女優の中でもっとも印象深かったのはカッティング・マニアの20歳の女の子。カットと言っても自分で手首を切るような生易しいものじゃなくて、プレイ相手にカッターで全身をきざまれるような行為にエクスタシーを覚えるような命がけのカッティング・マニアだが、彼女の場合は、それがなければ自殺していただろうという非常に逆説的な存在であった。
あるいは、スカトロ・マニアのある女の子は本当にもりもりと糞を食うのである。プライベートでは経験がなかったが、AVに出ることでそういった一種の自損行為を経験し、やがて、食糞しなくても普通に生きていけるようにアブノーマルな世界を卒業していった。
変な言い方だが、AVにやってきたそういった女の子たちははやまって死にさえしなければ卒業していく存在なのである。
しかし、みゆきはと考えると、最初から死んでいるようなものではないか。彼女には卒業も死もなくて、ただずっと不毛な現実が続くばかりである。
同じ事務所の食糞する女優がなんだというのだろうか。そのライバルが卒業していった後、やはりポツンとみゆきは取り残されているに違いない。
撮影の数ヶ月後、くだんの事務所のマネージャーからみゆきが撮影現場を放り出して消えてしまった話を聞いた。キャンセル代やペナルティーなどが残ったみゆきはその後何ヶ月も追い込みをかけられることになる。SM業界にいることは不可能だろうし、当然、AV業界からも姿を消さなくてはいけない。
しかし、みゆきは生きていかなくてはいけないのだ。老グルーピーたちが発していた得たいの知れない気持ち悪さをみゆきが発していたいたのはこういうことだったのだろうか。
第8回
グルーピーの女王と呼ばれていたある女の行き方
グルーピーの女王と呼ばれていたある女の行き方
みゆきはムチムチのフトモモを超ミニのスカ―トから剥き出しにしながら、有名な外人ギタリストの写真をぼくに見せてくれた。しかし、そんな彼女の生活は崩壊寸前だった。
あやしげなモデル事務所からやってきたその企画女優にはどこか見覚えがあった。名前は思い出せない。どこで会ったのかも見当がつかない。しかし、いずれにしてもどこかで会った女だった。
そして、その女は今床に座って、他の女優がコップに出した黄色い液体を目の前にしんぎんしている。撮影はSMビデオ。彼女は別の女優にいじめられるメイドの役で、今、ご主人様がオシッコをしたコップを目の前に置かれて困り果てているというわけである。
カメラは回り続けている。しかし、その女優はコップを手にしたものの、どうしても飲めない様子で、中の液体をジッと見つめたままかたまっていた。そして、時々、こちらを見て「本当に飲むの?」といった表情で助けを求めてきた。
もちろん、こちらは内容をモデル事務所に伝えた上での撮影である。飲んでもらわなくては困るわけだから、同情はしない。こちらも表情で「ダメ、ダメ、早く飲んで」と伝える。
すると女は絶望的な顔つきで、「ハアッ」と大きなため息をつくと、観念してコップを口元まで持っていき、液体を一口分流し込んで、オエッと吐き出した。
やがてぼくの頭の中にこの女が誰だったかあざやかに蘇ってきた。
みゆきだ! なんのことはない3日ぐらいだったが、いっしょに住んだこともある女じゃないか。あまりにガリガリにやせていたのでまったく気がつかなかったが、これはまちがいなくみゆきだった。
撮影の後で聞いたら、みゆきの方はこちらに気がついていたとか。しかし、ぼくがわかっていないようなので、そのまま黙っているつもりだったそうである。
みゆき…。彼女の名前を思い出しても、あたたかい思い出は何もついてこない。15年以上も前の話だったろうか、その頃、ぼくはまだ若気のいたりで柄にもなく音楽雑誌のライターなんかしていて、たまたま外タレ・グルーピーの特集をすることになって、その担当をぼくがすることになったのだった。
グルーピーってなんだ。日本人のタレントのおっかけとは全然様子は違いそうだが、あまり知識のなかったぼくは、その時までは、ただ、外人タレントが来日するとホテルに押しかけていって、あわよくばセックスをする女の子たち、といった程度の認識しかなかった。
ところが、これが取材を始めてみると想像していたのと全然違うわけである。
まず第一に、彼女たちはタレントのファンでもなんでもないということ。一日中タレントたちの宿泊先のホテルにたむろっているわけだから、当然、彼女たちは肝心のコンサートには行っていないわけである。
大事なのはタレントが大物かどうかということ。大物と一発やったというのが彼女たちのステイタスになるのであった。だから、世間一般的に考えられているように好きなタレントと肉体関係を結びたいといったある意味恋愛的な感覚とは彼女たちの行動はまったく関係ない。
次に驚いたのが、このグルーピーの世界というのは、ファンたちと一線を画する一つの集団で、タレントが来日すると全国から集まってきて、全員が顔見知り。ある意味「業界」のようなものになっていたことだった。
東京なら京王プラザホテルとか赤坂プリンスといったホテルに外タレはよく泊っていた。もちろん、宿泊先はオフレコなのだが、どこから漏れるのか、来日の当日となると全国からグルーピーの女の子たちが集まってきて、昼間からロビーや喫茶室や廊下で我慢強く機会を待っているである。
余談ではあるが、この時の主催会社の警備担当員とグルーピーの攻防は実に見もので、警備の幹部もグルーピーもお互い顔見知り。タレントの登場前にはこんな恫喝場面も。
「お前よ、今度強引なことやったら、裏連れてって徹底的にシメるからな」
しかし、タレントが現れるや、そんな恫喝など一切関係なしに大騒ぎとなるのだが、実は、グルーピーにとってこのような表舞台での喧騒は見せかけの行為にすぎない。
彼女たちの本領はこういう騒ぎを尻目にタレントの部屋に忍び込んだり、ちゃっかりタクシーに便乗して、ディスコに同伴してしまうことにあった。
いくら恫喝を受けようが、タレント本人にお墨付きをもらえば主催会社の担当もなんともしようがないのであった。
タクシーの後姿を見ながら「あの野郎、今度こそぶっ殺してやる」と歯軋りする男たちを何人も見た。
そして、みゆきはそんなグルーピーの中でも主催者が札付きの悪と認めて、目の敵にしていた女だった。
みゆきの得意は、タレントの部屋に強引に入り込んで、警備員が引きずり出そうとする時にはすでに目的のタレントの腕にしがみついているというものすごく強引なものだった。
一つには概して裕福な家庭に育って、英語が堪能な他のグルーピーたちと違って貧乏な家に生まれて、学歴のないみゆきは英語がほとんどできず、接触のためにとるべき手段を何も持っていなかったというのもあった。
しかし、いずれにしても、こんな荒ワザを使うみゆきだけに、荒っぽい警備員たちからはしょっちゅぅボコボコに殴られて、アザだらけの顔をしていることもあった。
ぼくが取材の相手としてみゆきに目をつけたのは彼女がこんな風にひときわ目立った存在だったからである。
下着の見えそうな超ミニにけばい厚化粧。グルーピー業界だけのファッションであるが、ホテルに行くとこんな女たちが何人もいて、まるでホテルがいきなりエロス・センター(ドイツの公設娼婦待機場)になったかのよう。
驚いたのは彼女たちの中にあきらかに40歳近い年齢の女もいて、みゆきの話では「あがれない」グルーピーはこうやって何十年もグルーピーを続けているそうである。
話が長くなったが、みゆきを理解するためにはまずどうしてもグルーピーの世界を理解しておいていただかなくてはならなかったのである。
みゆきの自慢はベッドでいっしょに撮影したタレントとのきわどい写真である。ぼくは全部見せてもらったが、なるほどそうそうたる顔ぶれがにやけた顔でみゆきとピースしていた。
へえ、こんな世界があったんだ…というのがその時の感想だった。
しかし、そんな歌舞いたハレの場がある一方で、当然、グルーピーたちにも生活の場というのがあったわけである。
先に書いたように、概して外国のタレントを好きになる女の子たちには裕福な家庭の子が多くて、生活に困っているような様子はあまり見られない。
しかし、中にはみゆきのような裕福とは縁のない育ち方をしている女たちもいたわけである。貧しいとか生活に苦労しているという言葉はグルーピーの中では禁句である。
みゆきもせいぜい見栄を張っていたが、実態はその日暮らしのホームレス寸前である。第一、なんでぼくがみゆきとプライベートでも親しくなったかというと、取材が終わって何ヶ月もたった頃、彼女から電話がかかってきたからだった。
「覚えてる? みゆきだけど、ちょっと頼みがあってさ」
こういう時の頼みなどというのはたいていが借金である。
病気になって簡単な手術なんだけど保険に入っていないので、お金が足りなくて…退院したらすぐ返すから4万円貸してくれる? と電話してきたAV女優。明日返すといって8万円持って行ったストリッパー。みんなそのままである。結局のところその日返さなければいけない町金融の目先の金なのだが、こんなことが重なるうちに女には絶対に金を貸さなくなってしまった。
しかし、みゆきの借金はそんなレベルじゃなかった。15万円貸してくれと言ってきたのだが、要するに、これは彼女の一月丸ごとの生活費である。かわりになんでもするからと言われても、そんな気分になる女じゃないのだ。
ただ、それでもみゆきはまだ踏みとどまっていた方かもしれない。こうしてみゆきと会うようになって、ぼくは実はグルーピーの「最底辺」というものを知ることになる。
ホテルではさんざん着飾り、高級ブランド物のバッグを持ち、外タレご用達の高級レストランに出入りしているこの女たちの生活のなんとまずしいことか。
みゆきと会っていると、彼女のまわりには同じような家庭環境で、生活に汲々としている連中ばかりが集まっているのに気がつくようになった。
彼女たちがかろうじて風俗に走らないのはひとえに「日本人とやりたくない」の一念だけだったのは驚嘆に値する。SMクラブの女王様たちと話をしていると、グルーピー出身者が多いが、これなども男にさわられない風俗ということで入ってきたと考えると説明がつく。
しかし、みゆきたちの困窮は最後のプライドまでいつの間にか崩し始めていく。かおりというヘビメタ好きの女がまず赤羽のピンサロで働き出した。するとそれをきっかけのように、次から次にみゆきのまわりは風俗嬢になっていく。
ぼくから15万円引き出せなかったみゆきもいよいよ追いつめられていた。
第7回
かおりの病状はいっこうによくならなかったが
かおりの病状はいっこうによくならなかったが
マリア様と呼ばれたかおりは妊娠中絶手術の後も長い間ベッドから立ち上がることはできなかった。その間にお見舞いにやってきた仲間の女の子たちのやさしが切なく。
マリア様はこれからどうするんですか?
という文章で前号は終わっている。マリア様とみんなから呼ばれていたかおりが実際この後どうしたのかというと、別段何も変わらず、やはり同じように淡々と時間が流れていくのがここに登場する企画女優たちのある一つの典型であった。
もちろん、淡々という言葉で表現されるものは普通の家庭に生まれて、普通に育った同世代の女の子たちと較べるとその密度においても激しさにおいてもまったく内容の違うものだったが、そんな自虐的な出来事が毎日日常の中で繰り返されていくということそのものが「淡々」という言葉の中にあらわされているのだった。
実際、何人もの男が出入りし、仕事といっても決して安全が保障されているわけでもなく、その上、病弱な体の上にアルコールに依存し、そして、母親に見捨てられ、今、中絶手術の途中にぜんそくの発作を起こして生死の境から戻ってきた22歳の女の子の目の前にいて、ぼくが感じることができるのは、これが彼女の唯一の生き方なんだということしかなかった。
しかし、実は、淡々というのは救いでもある。
かおりとぼくを乗せたタクシーは世田谷の彼女のマンションに到着したわけだが、ぼくがかおりを抱きかかえて部屋のベッドに寝させてやり、その横でぼくがビールを飲みながら雑誌を読んでいる姿は、つい数日前のいつもの景色となんら変わるところはなかった。
しかし、それでもさすがに中絶手術とぜんそくの発作のダブルパンチはかおりには相当こたえたようで、翌日もその翌日もかおりはベッドの中でおとなしくしていた。
ただ、本人はおとなしくしていても、次第に周囲がにぎやかになってきた。ぼくも顔を見知った仲間の女の子たちがお見舞いに現れ始めたのだ。恭子、由美、めぐみ、祐子、しのぶ…。みなフリーのモデル、あるいは女優たちである。
20年も昔のその頃は今と違ってモデルたちはほとんどがフリーで仕事をしていた。モデル事務所というのもあったが、現在のプロダクションのように芸能プロダクション同様に女の子のスケジュールを管理し、売れそうな女の子が入れば、単体女優として売り出すために専属のマネージャーをつけて戦略的にAVメーカーをまわるような組織的なものではなかった。
このたぐいのプロダクションが登場するのは84、85年頃に秋元ともみや渡瀬ミクといったそれまでのAV女優のイメージを打ち壊すような美少女たちが登場して、AVがメディアの表舞台に飛び出して以後の話である。
それまでの事務所といえば、個人的に女の子たちのプロフィールをあずかって、出版社やビデオ会社をまわるという程度で、女の子たちの側からすれば営業を委託しているといった感覚だった。なので、複数の事務所に彼女たちのプロフィールは置いてあったし、また、フリーとしても仕事を受けていたのである。
言ってみればかおりのもとに集まった女の子たちは当時のフリーモデルの互助会のようなものであった。お互いに仕事をまわしあい、危険な取引相手の情報を交換し、また、病気やケガをした時などにピンチヒッターで出演するなど、そんなきずなで結ばれた仲間たちだった。みんな20代の前半だった。
全盛期の頃のビニ本や裏本に出演していたのはこの女の子たちである。
恭子は19歳で仲間の間ではとびっきりの美人だった。今なら十分単体女優として通用するような女の子だったが、数多くの裏本に出演している。
ぼくも何度か恭子と仕事をしたことがあったが、驚くほど我侭で、撮影をしていも単に寒い、喉が乾いたという理由で現場から消えてしまった。
しかし、これを我侭と呼ぶんだろうかとも考えることはあった。むしろ、無頓着という言葉を使うのかしら、と。なぜなら、恭子は撮影途中に昼食のある時など、衣装を着替えるのをじゃまくさがって、下着が丸見えのミニスカートのまま平然とファミレスについてきた。まわりの視線など一切気にしないで、機嫌のいい時はしゃべりまくり、不機嫌な時はただむっつりしていた。仕事はたいていの種類をこなしたが、唯一のNGが剃毛だったというのが印象深い。
当時の業界モデルたちは今のようにギャルでもイケイケでもなくて、何かエッチな記号を発信しているわけでもなくて、ごく普通の女の子に見えたが、でも、恭子は奔放なだけ切ない美少女だった。ぼくの世代よりまだもっと昔、芝居小屋の美少女というのがそんな存在だったんだろうか。
そして、由美。由美は恭子の妹分で、いっしょに家出して東京に出てきた18歳である。多分、当時、本当なら高校生だったんじゃないかと思うのだが、彼女はスカトロ・モデルである。
20年以上前、新宿に「清水」という喫茶店があった。そこはエロ本の撮影隊とモデルが待ち合わせするので有名な場所で、たいてい午前10時頃になるとそこかしこのテーブルで何組も撮影隊がお茶をすすっていた。
しかし、撮影といっても今ほど女の子が管理されていない時代である。フリーモデルといえば聞こえはいいが、自己管理している女の子ならいいのだが、前の日に遊びすぎた、朝起きたら雨だった、あるいは、ただ単に行くのがイヤである、といった理由で撮影をすっぽかす女の子もいるわけである。
そして、そんな女の子に遭遇して困った顔をしている編集者やカメラマンを見つけては、写真をハダカのまま何十枚も持って彼らのテーブルにいいよっていく老人の姿があった。
古い業界人なら誰でも知っているM老人である。彼がいつからこの仕事を始め、いつからこんな風に「清水」に現れ始めたのかを知る者はもう少ないだろうが、とにかくM老人は困り顔の編集者に近づいて写真を見せるのだった。
「いい子いるよお、ウンコするよお」
独特のイントネーションで語られるモデルの斡旋。そして、彼が「ウンコするよお」と言う時、必ずその指先には由美の写真があった。
しのぶは仲間の中ではいくぶんお姉さんだった。年齢は26、27歳。そのせいかかおりの面倒をよく見てくれたが、彼女自身も心に問題をかかえていて、年に一二度は自分が何をしているのかわけがわからなくなるらしく、そういえば、朝も昼も夜も深夜も問わず日に何十回も電話されて辟易することがなんどかあった。そんな時、しのぶの頭の中はターボがかかっているようになっているそうである。一つの思念が浮かんだと思ったら、それが猛烈なスピードで暴走するのである。非常にビジュアルな思念であると言っていた。
そして、めぐみ。彼女は小料理屋を一人で営む母親といっしょに生活していて、一番まともな女だった。家庭にも仕事にもうまく居場所を見つけているようで、安定した精神をしていたので、仕事も一番しやすいタイプだった。ただ、裏本の撮影で無理やり本番されたことを非常に怒っていた。
そんな仲間たちがかおりのマンションに一人で、あるいは、連れ立って毎日やってきた。
かおりはどうやら相当具合が悪いらしく、真っ白な顔をしながら、彼女たちを見つめていた。
病院にもう一度連れていった方がいいと言い出したのはお姉さん格のしのぶだった。
「かおりは腎臓が悪いから、どんどん弱っている」
絶句するのはぼくの方である。ぼくだって25歳をようやく過ぎたぐらいの小僧じゃないか。もういいかげんに解放してくれというのがその時のぼくの気持ちだった。
結局、かおりの容態はしのぶがそんなことを言ったまさにその夜に急変した。呼吸がおかしくなってきたかおりの様子に気づいためぐみが(たまたまかおりの部屋でゴロゴロしていたわけであるが)、救急車を呼んで、今度はまがりなりにもまともな施設のある市民病院に運びこまれた。
結局、かおりは一ヶ月以上入院して、ようやくこちらの世界に帰ってきたのだが、この話がまた不幸な話なのかというと、今回はめずらしくハッピーエンドで終わるのである。
22歳の女と25、26歳の男が共に時間を過ごしたと言っても、当然、そこには秘密があるのである。22歳の女は25歳の男より倍ほど大人の世界の住人である。
その大きな病院で、ぼくは見知らぬ中年の男に抱かれて幸せそうにしているかおりを見た。かおりの恋人と言われていた谷沢とはまた違う男。誰なのか結局ぼくは知らないままである。ただ、かおりはこの男とその後結婚して、子供もできた。
同じ時間と同じ空間にいながら、かおりの別の世界とまったく触れ合わずにパラレルワールドのように生きていた…ということの意味はなんなのだろう。
第6回
マリア様、あなたはどうしてそんなにやさしいの
マリア様、あなたはどうしてそんなにやさしいの
マリア様と呼ばれた女の子がいた。しかし、マリア様がどうやってこの世に現れたのか誰もわからなかった。妊娠中絶手術の日、マリア様はぼんやりと外を見ていた。
ものすごく古い話になる。AVがまだ今のようにメジャーじゃなくて、女優たちも特殊な人たちと思われていた頃。もう20年も前の話になるのかもしれない。その頃のAV女優には今のように名前などなくて、出演する雑誌、ビデオごとに適当な名前がついていて、ひどい時には同じ雑誌の中で同じモデルが違う名前で登場した、なんて時代のことである。
ぼくも20代だったそんな頃、業界にマリアと呼ばれる女がいた。
いや、厳密には「業界のマリア様」と呼ばれていた。なんのことはない、頼めば誰でもやらせてくれる、ということからマリア様と呼ばれたのだが、業界に長くいるとどうもこのマリア様というのは2、3年に一人ぐらい出現するようだ。
やらせる女なんかいくらでもいそうじゃないかと考える人もいそうだが、実は、マリア様と呼ばれるにはなかなか条件が厳しいのである。
本人が淫乱で誰とでもやりたがるというのでは単なる色情狂だし、もちろんやらせる相手に好みがあったのではマリア様にならない。つまり、マリア様というのは慈悲深く、どんなに不細工な男でも臭くて汚い男でもヤクザでもインテリでもジジイでも子供でも求める者には与えて惜しまない、そんな女がマリア様なのであった。
そして、今から書こうとする女はぼくが初めて知ったマリア様だった。彼女の名前はかおりといった。その頃22歳ぐらいで、髪が背中まである細身の弱々しい女だった。東京の出身だったが、親とは離れて世田谷のマンションに一人住いしていた。
最初にかおりと会ったのは業界モデルのインタビューのためにカメラマンといっしょに彼女のマンションに行った時だった。その頃すでにアル中気味だったかおりはインタビュー中もビールを飲んでいて、ぼくらもいっしょに飲みながらのインタビューになった。そして、インタビューが終わると、まったく自然に三人でセックスになっていた。
まずぼくがして、カメラマンが続いた。前戯などほとんどない若者らしいセックスだった。かおりはカメラマンに激しく突かれながら目をつぶってささやいていた。
谷沢さん、ああ、谷沢さん好き……。
谷沢さんとはカメラマンの名前ではなくて、ぼくたちが二人とも知っているAVメーカーの社長の名前である。インタビューでかおりはこの谷沢という男が好きで、もう一年以上不倫を続けていると言っていた。しかし、かおりのことを最初にマリア様と言ったのはこの谷沢という男当人である。カメラマンは自分の体の下であえでいる女が別の男の名前を言い続けるのに鼻じらんで、すっかりやる気をなくして、体を離した。その時かおりはもうスヤスヤと寝ていた。
これがぼくとかおりの最初の出会いであり、その後2年ほど続くすったもんだの始まりでもあった。
その頃のぼくはまだ20代の中頃で、金もなければ誇るべき実績もないただの青二才で、当然、女にもてるわけでもなく、性欲が起こると風俗に行くしか処理のすべがなかった。なので、ぼくは何度も何度もかおりを呼び出した。昼間でも深夜でもかおりは電話に出さえしたらいつでもタクシーでかけつけてくれたのである。
ある時は、新宿の飲み屋にかおりを呼びつけてタクシーでラブホテルに行った。そして、朝まだ寝ているかおりをほったらかしにして、仕事に出かけたりした。友達はひどいヤツだとぼくのことを叱ったが、そんな風な関係になったのはかおりのせいでもあった。
カメラマンといっしょに初めてセックスした数日後、ぼくは一人でかおりのマンションに遊びに行って、そのまま泊まってしまったことがあった。結局、女にもてない寂しい男である。セックスが目当てというより、恋人のようになりたかったのだと思う。少なくとも、ぼくと寝てくれる女なのだから、ぼくの彼女になってくれるかもしれないなどと甘いことを考えていたのだ。いっしょに寝て、朝を迎え、そして、かおりがぼくにやさしく微笑みかけて、コーヒーを入れてくれる。
ひどい世間知らずだったと思う。かおりは起こそうとするぼくを面倒くさそうにはらいのけて、じゃあねとだけ短く言った。
いっしょにすごした時間の意味というのを考えてみる。そうするとかおりとぼくは何も共有していなかったのだ。
それ以来ぼくはかおりの世界に不必要に入り込むことをやめて、セックスだけをかおりに求めるようになった。だから、ホテルからとっととぼくだけ帰ってしまうのは、ヒドイことでもなんでもなかったのである。朝の時間をかおりとぼくが共有する理由などないと、とりあえずかっこつけて言ってみたりした。
しかし、そんな二人ではあったが、かおりはこの頃から「みよしさんのこと好き」と言うようになっていた。もちろん、谷沢との不倫は続いていた。あと、ぼくの知るだけでも二人、三人はしょっちゅう会っているような関係を持っていた。そして、マリア様としての奉仕活動も相変わらずであった。
では、「みよしさんのこと好き」というのはなんなんだろう。ウソをついてこびるような女ではない。だから、本当の気持ちなんだろうが、言葉の感覚がどこか違っていた。
そして、「事件」が起こった。かおりが妊娠したのである。当然誰が父親なのかわかるはずもない。かおりの周囲の人間たちが「犯人捜し」を始めた。しかし、これは谷沢の「絶対、みよしだよ。お前責任とれ!」のツルの一声で、ぼくが父親ということになってしまった。
もちろん、絶対にぼくではないという根拠はない。ないけれど、なんとなく自分ではないような気がしていた。結局のところ1年ほどたってから、あれはどうやら俺らしいという男が現れたのだが、それはともかく、中絶手術には父親の立ち会いが必要ということで、ぼくが書類にサインをし、病院につきそっていくことになった。
中絶専門のような新宿の汚い病院の待合室でかおりを待っていた。ところが、すぐに終わると医者が説明したにもかかわらず、1時間しても2時間してもかおりは帰ってこないのである。そうこうしているうちに、医者が困った顔で現れ、ぼくを身内か? と確認してから、実は……と説明を始めた。
医者の説明によると、かおりは喘息の持病があって、麻酔をしている間に発作を起こして、手術が中断しているという。もう少し様子を見るが、ひょっとすると自分の手にはおえないかもしれないなどと言う。
どうしてたかだか25、26歳の俺がこんなところに居合わせなればいけないんだ。どうして母親も父親もここにいないんだ。
そういえば、かおりは前に母親の話をしたことがあった。「お母さんはすごいやらしい人で、さかりがつきっぱなしなのよね。私が生まれた時にはお父さんと離婚していて、その後もしょっちゅう男が変わって、何人の男を私のお父さんですって人に紹介したかわかんないわ」
そんなわけで、かおりはほとんど母親の母親に育てられて大きくなった。母方が資産を持っていて、土地つきの家に住んでいたのだが、長男夫婦が同居していたので、かおりと母親は庭にバラックの簡易住居を建ててもらってそこに住んでいた。母親は毎年のように男を追いかけて、そのたびにかおりは一人ぼっちだった。
ある時、何ケ月も音信のなかった母親が帰って来た時、かおりは彼女のあまりに変わり果てた姿にビックリした。顔中にヤケドの後がなまなましく残り、目や鼻がひきつれている。
「男に捨てられて、その腹いせに男の家の前でガソリンかぶって自分に火をつけたって言ってた。どうしようもないバカなんだよ」
だから、かおりが今死ぬかもしれないという時も母親はこのようにいないのだ。この話を聞いた時はすごい話だといった程度に驚いただけだったけれど、今、こうして母親の不在について考えた時、22歳のかおりが経験してきた理不尽というものに思いをはせずにはいられなかった。
病院では、何科の医者かわからないが2人の若い医者が応援にかけつけていた。待合室でさらに1時間ほど待って、ようやくかおりが移動ベッドで運ばれて手術室から出てきた。かおりは真っ青な顔をして眠っていた。
ぼくは病室のベッドでかおりが目覚めるのを待っていた。やがてかおりがうっすらと目をあける。麻酔が冷めて傷が痛むだろうに、そんなそぶりも見せずに、黙って帰り支度を始めるのであった。事情のあまりよくわからないぼくは医者のところに行って、もう帰っていいのか、入院はしなくていいのかと質問責めにしたのだが、医者は家で安静にしてくださいとだけ言った。
かおりをタクシーに乗せて世田谷のマンションに向かう途中かおりの顔をチラッと見たが、かおりはぼんやりと前を見ているだけだった。
マリア様はこれからどうするんですか?
第5回
清純なロリ女優が少しの隙間から見せた暗黒
清純なロリ女優が少しの隙間から見せた暗黒
彼女は親孝行な娘といわれた。みんながほめていた少女だった。だけど、ぼくには本当のことは何もわからなかった。そんなことは誰も知らなくていいのかもしれない。
企画女優の連載も少し悲しい内容ばかり続いたので今回はこんな女もいたという話をしよう。ロシアには馬の目のようにかわいい目をした女という言い方があるのだが、今、彼女の特徴的な目のことを書くとするとこの表現しか思い当たらないかもしれない。
それぐらい大きな目にフランス人形のようなまつ毛。といってもフランス人形という形容詞もまた死語同然となった今、愛の顔の造作をなんと言えばいいのか。ま、要するに、大きなお目々にパッチリまつ毛。いつも黒目が涙っぽく濡れていて、その目で見つめられるとたいていの男は勘違いしてしまう、そんな目の持ち主が愛だった。
それなりの美少女だったのでデビューは単体女優。監督が気持ち悪くて、出演をした女優は全員泣くので有名だったメーカーの作品にセーラー服姿で出演。暴力を振るうわけでもなく、暴言を吐くでもないのにネチネチ、ネチネチした性格といやらしさが体中からブチュブチユと出てくる監督のハメ撮りにやはりシクシクと泣き出す愛。愛を初めて見たのはこの時だった。
ぼくはその時雑誌の仕事でいろんなメーカーのAVを評論する記事を書いていたのだが、たぶん、女子高生の役が似合うとっても清純な少女愛ちゃんが……みたいな原稿を書いたような気がする。
ところが、その2年後、この清純少女はロケ地に移動中の乗用車の後部座席で一目もはばからずぼくと生でバコバコとセックスをしていた。狭いシートでずっとハメたまま移動し、スタジオについてもまだハメたまま。カメラマンはあきれるし、メーカーの人間も苦笑するしで、えらく顰蹙をかったのだが、会ったその数十分後からこうなってしまったのだから愛とぼくはよっぽと相性があったのに違いない。
しかし、それでも愛の印象は「淫乱」というのとはほど遠いもので、清純という方がイメージにあっていたのだ。
実は、愛のその頃の生活は驚くべきものだった。清純な見た目からは想像もできない生活の一端をご紹介すると。
愛の本業は風俗嬢である。AVの撮影のない時は、午前10時から午後5時までヘルスで勤務、続いて6時からはピンサロへ。ピンサロがしまった後は営業時間が風営法と関係のないホテトルで朝まで。ここで仮眠をとりつつ、朝番のヘルスへと出勤していくわけである。
さらに10代の頃は早朝に新聞配達までしていたというのだからこれは驚きを通り越して驚愕。
で、その合間にぼくとセックスまでしているわけだ。
実は愛が風俗やAVの世界に入ってきたのにはそれなりの理由があった。田舎で父親が経営していた工場が倒産。5000万円ほどの負債をしょったのを愛がすべて返済しようとしたのである。さらに、愛には兄と弟がいて、それぞれの学費まで面倒を見ていた。
当時、この話は雑誌のインタビューなどを通じて有名で、現代版孝行娘としてみんなが愛のことをほめていた。
確かに、立派な話である。しかし、ぼくとしてはやはり釈然としないものがあって、いくら背に腹はかえられないといって、実の親が娘が風俗で稼いだ金を受け取れるか? とか、そもそもこんな話できすぎじゃないか?
結局、この話が本当がどうかなんて誰も確かめようがなかったわけである。事実は、愛が朝から晩まで働いていたということ。これならぼくが証明できる。なぜなら朝のヘルスにも夕方のピンサロにも深夜のホテトルにも客として行ってみたから。
結局、まともに会う時間がどこにもなかったのだ。
自分で言うのもなんだけれど、愛は間違いなくぼくのことが好きだったと思う。いつも見つめ、見つめ、見つめ、見つめていた。大きな目で。
なんて話は単なるセンチメンタリズムで、確かに、愛はいつもぼくを見つめていてくれたけれど、その直後にはもう商売人の顔になっていた。結局この人たちはいつも多重人格的なのだ。
単にやらしいオヤジに言い寄られただけでシクシク泣き出す清純なセーラー少女が一目もはばからずセックスしまくり、朝から晩まで風俗で働き、そしてものすごい勢いで金を貯めていく…。
しかし、当然のことながら愛のそんな生活は破綻する。知り合って4年ほどした頃、いきなり愛と連絡がとれなくなった。所属するモデル事務所に聞くと過労で倒れて緊急入院したとか。幸い、親しくしていた事務所なので入院先を知ることができたのだが…。教えられた病院の面会時間に病室を訪れてみるとドアに愛の本名の書かれた名札があって、どうやら4人部屋に愛が一人だけでいる様子。
そっとドアをあけて中を覗くと、ベッドまわりのカーテンがしめられていて、寝ていると思ったぼくはベッドに近づいて、カーテンの隙間から中を覗いた。
愛はいた。しかし、愛は一人じゃなくて、誰か見知らぬ男に抱かれながらスヤスヤと寝ていた。男の方は起きている様子で、さかんに愛の髪の毛をなでていた。ぼくはあわててその場を離れ、病院を後にした。
事情の多い女だ。こんなこともあるだろう…。だけど、それじゃぼくを見つめてくれたあの目はなんだったんだ?
それから一週間ほどしてぼくは再び愛をお見舞いすることに決めた。今度は男がいても愛に声をかけよう。お見舞いの花を渡そう。
そう思って病院を訪れたのだが、病室には愛の姿がなく、かわりに目つきの悪い男が一人パイプ椅子に座っていた。
「○○子は検査中だよ。お兄ちゃん誰?」と男は煙草とアルコールでガラガラになった声で言う。こちらを値踏みするような目で、少しだけ威嚇を込めながら。
直感的に「こいつとかかわるな!」と思ったぼくは、ただ仕事関係の知り合いで、店から花を届けただけだと言いおいて、すぐに部屋を出た。背後で男が花束をドサッと無造作に空いた椅子の上に投げ出したのを感じながら、いまだ緊張したまま廊下を歩く。すると、角を曲がるところで偶然にも愛と出くわしたのである。愛はさっと顔色を変えると、ぼくに気がつかないふりをして足早やに横を通り抜け、自分の病室の方へと走り去っていった。
病んだやつれた精気のない愛のスッピンは疲れた朝のホステスの顔だった。
ぼくはこの日以来愛を見舞いに行くのをやめた。
しかし、事態はこの後大変なことになったのである。
愛は退院してすぐにピンサロで働き始めた。そして、すぐにぼくに電話がかかってきた。連絡を受けて、店に遊びに行ってみると、愛はぼくの顔を見るなりいきなりワッと泣き出して、ぼくにしがみついたまま離れなくなってしまっのであった。困惑する従業員。ぼくだって困惑する。その場はなんとか収集し、店が終わった後、ぼくが愛を送ってやることになったのだった。
そして、夜の12時すぎの繁華街をいっしょに歩いていると、ぼくたちはヤクザというより20歳そこそこのチンピラ風の兄ちゃんたち三人ほどに取り囲まれた。
中の一人がいきなり愛の腕を引っ張って、道のはしに連れていき何やらわめいてる様子だったが、こちらと目があうや突然走ってきて、
「テメエ、人の女となにやってんだよ! ぶっ殺されてえのか。この女、俺の女房なんだよ、えーっ!」
人の女? 女房? 間に入って止めようとした愛をいきなり蹴りつけて、ドサッと路上に倒れる愛。すでに黒山の見物人である。
男はぼくの胸倉を掴んで、今にも殴りそうな様子だった。しかし、そんな緊迫した事態がなぜか他人事のように感じられていた。
ぼくの中で何もかもがくずれていった。親を助けるために一日中風俗で働いた女、無類のセックス好き、しかも、この頃には彼女は忙しい合間をぬって小さな輸入雑貨の会社を作って社長にまでなっていた。そして、病室で添い寝していた男、ヤクザ、そして、今、目の前の「夫」と称する男……。
これが愛との最後である。一度だけ、愛から電話のかかってきたことがあった。ぼくは聞いてみた。
「あの時のお兄ちゃん、本当に愛のダンナだったの?」
「迷惑かけてごめんなさいね。19歳の時に一度結婚したんだけど、すぐ離婚した相手なんですよ。しつこくて困ってるんだけど」
「ふーん、今、何してるの?」
「会社が増えて忙しくやってますよ。もう自分では店出てないですよ」
と、笑う愛。結局会社のかけもちで朝から晩まで働いているのは同じだそうである。そして、入院という愛の時間の隙間から覗いたヤクザやヒモやチンピラたち。中途半端にカタギのかかわる世界ではないのだと思う。
第4回
すさまじく残酷に人生が変わっていった10年
すさまじく残酷に人生が変わっていった10年
レストランで由加里と話ながら過去がどんどん蘇ってくる。あの時由加里にまとわりついたマネージャーは、婚約者は……。今、由加里は静かな世界でひっそりと暮らしていた。
そもそも由加里はAV業界に対してはあまりに無知であった。AVの世界はまさしく有象無象だ。裏ビデオもどきの制作会社から大手企業と呼べるようなAVメーカーまで何百という会社があり、監督や制作スタッフにはテレビや映画出身者、ブルセラショップからの転業組、単なる脱サラから元風俗店の店長。難関大学を卒業したインテリから少年院帰りまで様々な経歴を持った男たちが集まり、さらにそのまわりにはモデル事務所やスカウトのグループと、一筋縄ではいかない有機的なつながりを持った複雑な社会だ。
多くの企画女優はそんなことを何も知らずに業界に入ってきて、数本出演しただけで消えていく。
しかし、由加里の場合は少し違った。それが彼女の運命を何度もつまずかせることになるのだが。
実は、由加里はAVプロダクションに入るずいぶん前に例の「ストリップ好き」が高じて劇場の門を叩いたことがあった。ゆかりが18歳の時、高校を卒業してすぐのことだ。同級生を集めてアソコを見せているだけではあきたらなくなった由加里は、ただ自分のハダカを見せたいというそれだけの動機につき動かされて、ストリップ劇場がどんなものかもまったくわからないまま突然出演させてくれるように劇場に現れたのだった。
劇場に紹介されて由加里はあるモデル事務所と契約することになる。そして、ストリップのワンクールにあたる10日間だけ踊って、とっとと姿を消してしまった。
困ったのが事務所である。次のクール、次のクールとすでに予定は入っている。しかし、まったく世間知らずの由加里にはもちろん「仕事」などという観念があるはずもないのだ。事務所の方では由加里を探そうにもまだ携帯電話も普及していない時代で、家に電話しても誰も出ないわ、実際に行ってみても年寄りが出てきて要領を得ないまま。結局、この件はうやむやのまま終わった……ように思えたのだが、それから何年かして由加里がAVプロダクションに入った時、この時の件が再燃する。
なんと新しく所属した事務所とかつてトラブルを起こした事務所が系列会社だったのだ。そんなことをまったく知らずにある日いつものように事務所にギャラを貰いに行った由加里の前にかつて自分を劇場に連れていったGというマネージャーが待っていた。Gにしてみれば千載一遇の機会。その場でGに拉致された由加里は彼の事務所に連れていかれて、ボコボコに殴られることになる。
お嬢様育ちの由加里が平手打ちならまだしも男に拳骨でしかもおもいっきり何度も殴られるなど初めての経験だったのではないだろうか。
結局、由加里は昔自分が勝手にキャンセルしてつくった損害をAVに5本出演することでチャラにしてもらうことになる。そして、本来の事務所に戻った由加里だが、今度はこちらの事務所のFというマネージャーが由加里に色目を使い始めた。風俗でもモデル事務所でも本来が店内風紀はご法度だ。しかし、現実には同じ世界で恋愛になることは珍しくない。とはいえ由加里には婚約者がいた。
もうここからはごちゃごちゃのお決まりのパターンだ。AVをやっていることに気がついた婚約者が由加里をやめさせようと事務所にかけあう。しかし、こちらは百戦錬磨のツワモノである。特にマネージャーにとっては由加里を自分のものにする最大のチャンスだ。
後で聞くとこの件はおおもめにもめたらしい。マネージャーというのが相当に粘着質なタチの悪いヤツで由加里の婚約者をしつこく狙って、結局、仲間と襲撃して重症をおわせることになる。その間、由加里自身にも大変なプレッシャーがかかっていたと思うのだが、しかし、そんな時にも由加里はぼくに会って、なにごともないようにホテルでセックスしていたのだった。
ずっと後になって聞いたのだが、マネージャーのFはぼくと由加里の関係に気がついていていたらしい。この世界では女優やモデルが制作スタッフと関係を持つのはご法度である。ぼくのまわりでも毎年誰かがこの種のトラブルを起こす。場合によってはかなりやっかいなことになったりもする。
しかし、Fが大好きで大切なぼくを攻撃するかもしれないとわかっているにもかかわらず、また、それ以上に婚約者との間に真剣なトラブルをかかえているにもかかわらず、由加里はどうしてこれらの騒動に無関心でいられたのだろう。まるで、当事者は自分ではないというように。
「由加里、みよしさんのこと大好き」などと言ってベッドでくっいていられたのだろう。
しかし、その頃由加里はしょっちゅうぼくに電話してきて、夕方に会っては食事をした後ホテルに入った。
その頃の由加里はまだ男性恐怖症にはなっていなくて、こちらの少し変態っぽい要求になんでも答えてくれた。とは言っても基本的にはマゾっ気の強い女なので、ぼくの方が命令しては従わせていたという関係なのだが、一つだけ困ったのがスキンをつけてハメるのをいやがったこと。
愛撫して、たっぷり濡れたのを確認して、肉棒にコンドームをつけようとすると、必ず由加里はそれを手でおしとどめて「イヤ! 生でして!」と言うのだった。
あるいは、こっそり装着して挿入した時など、ピストン運動している股間に手を伸ばして、そのままはずしてしまったりした。仕方がないのでぼくはそのまま激しく腰を振り、ドクドクと精液を由加里の膣深くに流し込んだのだが、これもいったいなんだったのかぼくにはよくわからなかった。
結局、この騒動はマネージャーFの逮捕と由加里の事務所移籍、そして、婚約解消という形で終わりを迎えた。いや、実際は、この後、Fが戻ってきて今度は風俗店を始めた時に由加里がイメクラ嬢として手伝ったり、婚約者とよりが戻ったり、再び、前の事務所の別の男にストーカーされたりと、まったくすっきりしないまま2年、3年と流れていったのであったが、その間の詳しいことはあまり知らない。
もうそれからはポツ、ポツとしょぼくれたにわか雨のようにしか会っていなかったから。そして、新宿のレストランで「初めて自分が悲しいと思いました……」と言われた夜、ぼくたちは久しぶりにホテルに行って抱き合った。
と言っても、男性恐怖症がやっとパニックを起こさないといった程度に回復している状態の由加里だったので、ずっと手をつないでいただけだけれど、最初会った時の由加里は本当に世間知らずのお嬢様だったのに、6年の歳月がすっかり彼女を大人にしていた。しかも、ボロボロの……雑巾のような。
結局、経験が人間を大きくするというのはウソのような気がする。大きくなることもあるし、全然そうじゃないこともあるというのが本当のところじゃないだろうか。つらい経験はそれがつらすぎると毒にしかならないのだ。
そして、由加里の場合はと言うと、彼女は確かにボロボロに打ち負かされた人間ではあった。しかし、彼女の育った精神的な環境と経済的な環境が彼女に与えた心の豊潤さは彼女の魅力として今なお輝いていた。
由加里ははたして復活するのだろうか?
今、由加里は絵画のモデルをやりながらフラメンコ・ダンサーとして熱心に練習している。練習は週に4回。すでにプロとしての舞台も何度か踏んでいて、ぼくも一度見に行ったことがあったが、何かに憑かれたような由加里のダンスは、その無気味さが観客たちに伝わるようで、他のダンサーたちに対する態度とはまったく別のとまどったような反応を見せていた。決してうまいわけではないが、神がかりのようなダンスなのである。
そして、ぼくはこんな風に思うわけである。今、ステージの上で踊っているちょっとおかしな雰囲気のダンサー。といっても、普通に町を歩いていれば、誰もふりむかないような平凡な女の子の歩いてきた時間の中にこんないろんなことがあるなんて誰が想像するんだろう、と。
たっぷりと寝た朝、由加里はぼくのそばで可愛い寝息をたてていた。そうだ、由加里はもう帰らなくてもよかったのだ。結局のところ婚約者ともすっかり縁がきれた由加里は、母の事実上の失踪、そして大切に育ててくれた祖父母の死と、再び、人生の試練にむかいあい、人格をバラバラにしてしまいそうな様子である。結局、由加里とは彼女が完全に消滅してしまうまでこんな風にしてつきあうんだと思う。ぼくの中の切ない感情さえ枯れかけていた。
第3回
人形のように可愛らしい由加里の中の「淫乱」
人形のように可愛らしい由加里の中の「淫乱」
仮面症と診断された由加里との長い時間の中になぜか時々ポッカリと空く空白。ぼくのまったく知らない生活が彼女の中にあって、それがぼくをとまどわせるのだった。
「初めて自分が悲しいと思いました……」
由加里から連絡のあったのは長い間連絡がとれなくなってもう忘れかけてしまった頃だった。プルル、プルルと変哲のない携帯電話の呼び出し音が鳴り、着信ボードに由加里の名前。
その夜、新宿のレストランで由加里に会った。由加里は28歳になっていた。そういえば、出会ったのは彼女が22歳の時。美人ではないけれど、仕種や表情が絵本に出てくるような「女の子」を強烈に意識した女で、なじみの店に連れていくと女将や大将から 「かわいらしい女の子だったねえ」と後から必ず言われる女だった。
つまり、そんな仕種が彼女の存在そのもになっていたわけだが、最初に出会うきっかけになった撮影のことはもう少し後に書くことにしよう。
とにかく、今、由加里はぼくの前に座っていて、涙ぐんだ目をしながら語っていたわけである。
「またやっちゃって……」というのは何度目かの自殺未遂のことだが。
「私がフワッと浮いていて天井から私を見ていたんです。テーブルの上に酒の空き瓶がいっぱいころがっていて、私がうつぶせになっていました。それを見た時、今まで一度も感じなかったんだけど、私が私のことをものすごくかわいそうに思ったの」
そして、由加里の目からあふれ出した涙が止まらなくなってしまった。号泣というのではなく、なんだろう、何かを洗い流すようにサラサラ、サラサラと流れ続ける涙だった。
由加里とはこんな風にして断続的に何年もつきあってきた。
いっしょに寝たのは最初の撮影の時だった。雑誌のカラミものの撮影で、打ち上げの後、一人になるとなぜか由加里がぼくの後についてくるので、それとなく肩を抱いて一緒に歩いた。
「ホテルに行く?」
「うん」
しかし、ホテルの前に着くと、「イヤ、イヤ」。
「じゃ、やめとく?」
「イヤ」
「じゃ、入る?」
「イヤ」
なんなんだこの女は! 要するに強引に誘われたいんだろ。と思ったぼくはとても面倒くさくなってきた。大体、テメエのやりたいマンコを他人のせいにしてするような女はもとから嫌いである。やりたいならやりたい。やりたくないならやらない。どちらかハッキリしない女は相手にはしたくなかった。
が……。結局、由加里はイヤだイヤだと言いながらホテルの入り口までついてきてしまったのであった。なんというか、イヤだイヤだと言っている間にイヤの対象がずれてしまって、最後には何にイヤなのか。誘うのがイヤなのか誘われないのがイヤなのか、言葉がドタバタになりつつ、ホテルへ。
そして、そんな風にしてぼくたちはホテルに入った。
でも、朝起きると横にいるはずの由加里はいなかった。あわててフロントに電話をすると朝早く一人で出ていったとか。ぼくが寝ている間に帰ってしまったのだ。
後で知ったのだが、由加里にはいっしょに住んでいる婚約者がいて、どんなに遅くなっても外泊するというわけにはいかなかったのだ。
由加里がAV女優になるきっかけはそもそもはこの婚約者だった。ヤクザな男ではないが、「一発当てる」というのが好きな男で、サギ師まがいの連中の甘言にのせられては大金をはたいて、ついに借金も500万円ほどに。それを返済するために由加里はAVプロダクションに入ったのであった。
しかし、男に貢ぐ女というイメージとは由加里はまったく違った。そんなに激しく男を愛しているようにも見えなかったし、貢いでまでその生活にすがっていたいようにも見えなかった。
なんとなく惰性が流れていた。
そもそも、由加里はお嬢様の生まれだ。父親は有名な画家。母親も世界をツアーしてまわるピアニストである。由加里も小さい時からバイオリンを習い、小学生の時にすでにクライスラーを楽譜なしで弾きこなし、数々のコンテストで賞をとっている。
彼女といっしょに遊んだ頃、楽器屋に立ち寄って楽譜を買うのによくつきあったが、企画AV女優とクラシックの違和感ってありますか?
実は、AV監督の仕事を長くやっていると、なんで君が? といった女優に出会うことが時々ある。基本的にはヤンキーっぽいノリのいいイケイケのお姉ちゃんたちが多いこの世界だが、由加里のような例が珍しいわけでもない。もっとも両親がここまで有名というのは珍しいけれど。
そして、よくあるように由加里の心の中には幼い時からずっと空洞があった。家にいない母親。中学生の頃に自殺してしまった父親。
結局、由加里はおじいさんとおばあさんに育てられたようなものなのだが、そんな空洞を埋めるかのように、由加里の性は暴走する。いや、暴走というより迷走というべきか。由加里の頭の中の性は現実的な性衝動ではなく、何かおかしな印象を与えるものだった。
「中学生になった時スカートがものすごく短くなったの。丸見えなの。同級生にも先生にも」
そして、由加里はついに近所の少年たちを公園に呼び出してストリップショーまでするようになる。オッパイはもちろんアソコまで開いて……。
由加里はその頃のことを淫乱な自分と言うが、それは淫乱というのと違うような気もする。しかし、由加里の頭の中のこの「淫乱」が精神のバランスを保つためには必ず必要なものであったのだと思う。
なぜなら、由加里が幸せだったと思った時間はいつもこの「淫乱」が彼女といっしょにいたからだ。今、28歳の由加里にはこの淫乱がいなくなってしまっている。突然男性恐怖症のパニックを起こしてから、淫乱の住む場所がなくなってしまって、自殺、アルコール中毒、疾走、入院と散々な日々である。
だから、由加里は貢ぐためにAV女優になったのではなくて、AV女優にならなければいけなかったのだ。
AVは癒しだとよく言われる。また、病院だとも。
これはもちろんAVを見る人にとってではなくて、出演する人にとってである。V&Rプロダクションという変態をいっぱい集めてビデオに出演させているメーカーがあるが、もうずいぶん昔のこと。あるスカトロ男優が亡くなった時、その人のお母さんがV&Rに感謝の言葉を伝えたそうだ。内容はずっと家にひきこもって、言葉さえ何年も一言も発しなかった息子がV&Rに出入りするようになってからは見違えるように明るくなって、ニコニコしながら出かけていった、と。
自閉症気味の女の子、対人障害の女の子、どこかしら心の傷ついた女の子たちが解放されていき、そして、退院していく姿はぼくもいっぱい見ている。本当にAV業界は病院だと思う。ただ、ぼくの立場は医者じゃなくて、結局、退院できない不治の患者のようなものかもしれないのだが……。
それはともかく、由加里のAV生活はこうして始まった。しかし、始まったと言っても世の中の仕組みなど何も知らないお嬢様である。
撮影に遅刻するのは当たり前。遅刻してもあやまるということを知らなかった由加里。撮影の段取りにおかまいなしに高価な食事を頼んで、みんなが待っているのに平気でゆっくりと楽しんでいる由加里。ついにカメラマンが切れる。涙を浮かべる由加里。しかし、後で聞いたら。
「なんで怒っているのかわからなくて泣いちゃったの」
ハッキリ言ってほとんど使い物にならないAV女優だったが、なぜかぼくは由加里が好きで、それはきっと彼女の寂しげなところにに魅かれたからだと思う。
「と思う…」という部分が実は大切なところなのだ。ぼくの前では由加里は芸術家の家で育ったかわいいお嬢ちゃんで、いつも抱きしめたくなる繊細な女の子だったが、つきあいも半年たち1年たつと彼女にはぼくがまったく知らない性格があることが、いや、もっとハッキリ言うと「生活」があることがわかってきた。
一つには彼女の婚約者との生活がある。仕事に出ていない時は家庭にこもって、家事にいそしんでいるという話だが、そのうち、彼女から深夜や未明に泥酔して電話がかかってくるようになった。背景にはカラオケがガンガン鳴り響き、今どこにいるの? と聞くと、埼玉県だったり千葉県だったり。何してるの? と聞くと「フフフ」と笑って電話を切ってしまう。
警察から電話の来たこともあった。ぼくの名刺がどこかからか出てきたんだろう。
その頃、病院に通い始めた由加里はこんなことを言っていた。
「先生があきれちゃって。仮面症っていうらしいんだけど、私って……」
仮面症ってなんだろう。いよいよ由加里はここから怒濤の生活を始めることになるのだが、正直、彼女との空白の時期については何もわからない。こんなに親しくて、何年もつきあっているのにまったくわからない。そんなことって可能なのだろうか……。
第2回
SMクラブで働き始めた淳子が女にナンパされた
SMクラブで働き始めた淳子が女にナンパされた
企画女優淳子と始まった半同棲生活だったが、それでも彼女の生活は少しも見えてこなかった。そして、事態は思わぬ展開を見せて、あっという間に終わってしまった。
ある時、淳子が自分をペットのように飼ってほしいと言い出した。その本当の意味はなんなのだろう。
ぼくと企画AV女優岬淳子が半同棲を始めてまだ一週間もたっていなかった。元々マゾっ気の強い淳子だからそんなことを言い出しても不思議ではなかったが、犬になりたいとか、檻で首輪をつけて生活したいとか、そんなことを本気で考えていたのだろうか。
マゾヒストには相手の心の中のサディズムを引き出す力が存在する。完全にその気がないなら別だが、少しでもあったら強烈な相手に出会うと自分でも知らないうちにどんどんエスカレートしてしまう。
どちらかと言うとぼくにはマゾヒスト的性癖が強い。なのに淳子を相手にしていると、淳子のマゾの方がぼくを圧倒してしまって、いつの間にか淳子を責め抜いている自分がいた。
全裸で目の前に立たせ、ビンタをくらわせ、針を取り出して、それでクリトリスを突き刺してやろうと脅すと、淳子は泣きながら「痛いのはイヤです!」と叫ぶ。しかし、ぼくは淳子の股間を見て絶句する。両脚の間から透明の愛液がツーッと糸を引いている。その糸は30センチも40センチも切れないまま伸びていて、淳子の股間でプラプラと揺れていた。
そんな淳子がペットのように飼われたいと言い出したんだから、それは本気とも嘘ともわからなかった。
もちろん、マンションの中に檻を持ち込むのも首輪をつけて彼女を飼うのも現実的ではないので、話は話で終わってしまったのだが、現実は小説よりも奇なり。なんとこの一カ月後、淳子は本当に首輪をつけて檻に入ることになったのである。もちろん、ぼくが心機一転ハードサディストになったからではない。なんのことはない淳子がSMクラブで働き始めたからである。
このSMクラブは少なからずぼくに縁があって、オーナーと古くからの知り合いだったことから、一部出資して、広告の方も担当していた。ま、もともとがホテル営業でプレイルームがいらない、電話一台あれば十分みたいな安易な店で、オーナーご本人が自分がやっていたキャバクラ倒産後のどうでもいいや感覚。手もとに残った300万円ほどの金で何かできそうなものはないかと考えて思いついた店である。なんにもノウハウがないから手伝えということでおつきあいすることになった店なのだが、これが究極のいい加減。
新宿にワンルーム・マンションを借りて、そこを事務所兼女の子の待機ルームにして、スタートしたものの、募集をしなければ女の子が集まってくるわけもなく、全部ぼくの個人的なつきあいでかき集めたSM嬢ばかり。淳子もそういう関係でかりだされたというわけである。
で、そんな店に客が来るわけないので、社長は毎日、毎日、カーペットの上に直接置いた電話をジーッと見つめているだけの生活。2、3人が交代で待機していた女の子もあまりのヒマさに次第に足が遠のき、予約が入ったら呼んでちょうだいと言ったまま他の店に働きに出てしまう始末である。
そんな中、淳子だけは社長といっしょにワンルーム・マンションに一日待機して、ジーッと電話を見つめていたのであった。
時々様子を見に行ったぼくだが、ぼくに会うたび社長が文句を言うのであった。
「みよしさん、なんとかしてくださいよこの女! メシばっか食って、メシ代だけで倒産しちゃうよ」
そういえば、部屋のドアの前にはいつも出前の食器が山盛りに置いてあって、4、5人分はあったのだが、考えてみればこの部屋の住人は社長と淳子だけ。アル中の社長はあまりメシを食わないから、どうやら淳子が一人で食べていたようなのである。
「昨日の昼なんか中華丼にラーメンにミニ・チャーハンだぜ!」と社長は淳子の頭をこずく。
いっしょに住んでいるといってもつぶさに彼女の生活を観察しているわけじゃないし、店が始まってからは一日中淳子はこちらにいるし、社長の話を聞いて、初めて知った淳子の食生活だった。
糖尿病なのにそんなに食べてどうする。様子を見ていると、ジュースの消費具合も相当なもの。
この時は「お前死ぬぞ」と言ったぼくだったが、重症の患者にはそれなりの糖分が必要で、無理にジュースを飲むのをやめさせたりしたらかえって低血糖の発作を起こして危険であるというのを知ったのは彼女と別れてずっと後のことであった。
ずいぶん悪くなっていたのだ。
しかし、それはともかく、淳子の性格はやはり変わっていて、それまで働いていたヘルスでは指名はなかったものの毎日5人か6人は客がついてそれなりの稼ぎがあったにもかかわらず、日がな一日ボーッとこの店に座っていたのである。とりあえず「恋人」のぼくが特に強制したわけでもない。頼んでみたら、いいよおとのんびりした返事でこちらに来ただけである。そして、毎日、何升ものメシを食っていた。
しかし、世の中にはやはり奇特な人がいるもので、そんな淳子にも週に一度彼女を指名する客がいた。その男が淳子に首輪をつけ、犬のようにして遊んでいたわけである。
結局、淳子はそんな生活を喜んでいたんだろうか。ゴロゴロした時間が本当に気の遠くなるほど流れていたような気がするが、実際にはほんの数週間がたっただけだった。
淳子とのさようならは驚くほど突然にやってきた。別れと言っても深刻さなど全然ない別れ。淳子のようなタイプの女の子たちは人一倍のさびしがり屋で、人のぬくもりを求めているようで、その実、ビックリするほどあっさりしていたりする。どこかで人間のつき合い方がおかしいのである。
だから、別れの日はこんな風だった。なぜかその日にかぎって店に出てこない淳子に、社長が電話をしたのである。
たまたま、店に顔を出したぼくに社長がこう告げた。
「みよしさん、ふられましたで。あんたとは別れたって」
別れたって……俺はなんにも聞いていないぞ。そうしたら、今度は社長がゲラゲラ笑いながらこんなことを言う。
「それで、あんた、自分の女を誰に取られたと思う? 女だよ、女! 新宿のおなべバーの女にナンパされて、一目惚れだって。みよしさんとはこれからもいい友達でいようねだって。あっ、それから、男には体に指一本さわられるのもイヤだってよ」
そして、最後に社長は笑うのをやめて、こう言った。
「店も終わりやね……」
これが淳子との顛末である。新しい男ができたのならともかく、あろうことか女に寝取られたというのはさすがにハプニングの多いぼくの人生の中でも前代未聞のできごと。さすがに納得がいかないぼくは、最初はその女に淳子がだまされているんだと思った。おなべバーの女といえば、言ってみれば女のホストのようなものじゃないか。じゃあ、うまいこと言われて、淳子はだまされているんだ……。
しかし、結局のところぼくはその後淳子に会わなかった。
淳子の姿を見たのは、それから一年以上もたった頃だった。しかも、ビデオの中で見つけたのであった。それはあるメーカーの作品だったが、露出教でスカトロ・マニアで女と同棲しているAV女優のドキュメントだった。
街の中を尻が丸出しのミニスカートで歩いている姿。その女の後をカメラが追っていくと、同棲相手の女とすごく幸せそうにキスしている淳子がいた。心なし顔つきが大人っぽくなって、以前のような病気っぽいブヨブヨした雰囲気もなくなっていた。
淳子は家庭を持ったのかもしれないとぼくは思った。奇妙な共同生活かもしれないけれど、実家にも男との生活の中にも見つけることのできなかった落ち着きを見つけたんだろうか。
それから5年ほどして池袋のある風俗店で淳子に偶然出会ったが、彼女との交際はまだ続いていると言っていた。お店はヘルス。しかし、フェラチオはゴムフェラ。
「口内発射などもっての他だよ」と笑ったが、えっ、そうだっけ?
新宿のヘルスで、頼まれもしないのに客のザーメンを飲んでいた淳子。ゴックンはオプションだよと教えられていても、お金をとれなかった淳子。彼女の選択は彼女の中で選べる最高の選択だった気がする。
と言っても今淳子が何をしているかなんてまったくわからない。明日にでもまたどこかの喫茶店でスカトロOKの企画女優ですとインチキっぽいマネージャーから紹介されても少しも不思議ではないのだ。
そういえば、淳子は一度ぼくを実家のそばまで連れていってくれて、こんな風に話したことがある。
「ここには15歳までいたけど、いつも家出ばかりしていて、お母さんも私のこと探さなくなったから、これはただの建物。友達のところにいても男といても私には夕方に帰るところがなかったから、一日がいつまでも終わらない感じなんだよね……」
かけ算はできなくても自分の言葉を持っていた彼女。さて、淳子の一日はいつ終わるのだろうか。
第1回
汚物女と卑しめられるほどに目があやしくなって
汚物女と卑しめられるほどに目があやしくなって
企画女優という言葉にはなぜか男の複雑な愛情がこめられている気がする。なぜかいとおしい存在なのにその理由はわからない。でも、少しでも彼女たちの本当の姿を知りたい。
岬淳子という女がぼくの前に現れたのは5年ほど前のことである。大久保の喫茶店にマネージャーに連れられてやってきた淳子は18歳で、目の玉の茶色いのが印象的な肌の白いポッチャリした女の子だった。初対面ということでおとなしくしていたが、完璧なサギ師面した30代のマネージャーの横でずっとニコニコ愛想をふりまいていた。
あーあ、こんな性格のよさそうな女の子はいつもこういうインチキな男たちのいいようにされちゃうんだなあ。とこれまたいつものようにステレオタイプな感想を抱きつつ、淳子を見ていたぼくだったが、この時にはまさかぼくが淳子とごく短い間だったとはいえ、濃厚な時間を二人で共有するとは夢にも思っていなかった。
実は、企画女優という連載を始めることになって、ぼくは何を書いていいのか最初のうちはまったくわからなかった。企画女優の歴史? 今はやりのインタビュー? それとも、露出マニアで中野の駅をアソコ丸出しでウロウロして警察に捕まったとか、渋谷のハチ公によじ上ってマ○コ、マ○コと絶叫してそのまま精神病院に連れられていったという本当にあったキャッチーなエピソードをおもしろおかしく書く?
AV業界は確かに脳味噌のぶち切れた女がいる世界ではある。特に、毎年何千人とデビューしては同じ数だけ消えていく企画女優たちの中に時として「マジかよ!」という女の子たちが大勢いるのも事実。
しかし、ぼくはなぜかそんなぶち切れた女の子たちばかりに取り囲まれて仕事をしている。これは偶然というより、きっとぼくがそういう女の子たちをとっても可愛いと思い、また、そんな気持ちが彼女たちにも通じるからお互いに寄り合うんだと思う。特に、一風変わった女の子たちの心の中は水でいっぱいである。なんかよくわからない表現だけれど、恋ややさしさや人恋しさや寂しさや思いやりがいっぱいつまっていてタポタポしているのに、いつも現実にはキ○ガイのようにしかなれない心過多な女たちの可愛さって……それはまさにぼくにとっての女神様たちだった。
だから、結局、ぼくは企画女優たちとの恋の話を書くことにした。それが一番彼女たちを伝えることができるからだ。
というわけで、そろそろ淳子に戻らなければ。大久保の喫茶店での出会いの後、仕事で淳子とあったのは2回だけである。
一度は特に変哲のない雑誌の企画撮影のモデルとして。女子高の制服を着せると高校に行かなかった淳子はとっても喜んではしゃいでいた。高校に行かなかったのは家庭の事情のようだが、教育は大切である。中国の首都は? と聞いたら、台湾と言ってまわりを唖然とさせた淳子。
そして、もう一つはマニアビデオの撮影である。この撮影はマニアックな中でも特にマニアックな内容でスカトロ。しかも、するだけじゃなくて、体中に塗りたくって街を歩くというある意味犯罪的なビデオであるが、こんな内容をOKした淳子に実はぼくは疑問を感じていた。サギ師の顔をしたマネージャー。その横でニコニコしているだけの淳子。淳子はなんにもわかってないんじゃないのか? 人のよさにつけ込まれてマネージャーにいいように言いくるめられているだけじゃないのか?
実際、撮影に際してそんなケースは決して少なくはない。現場に来るまで全然内容を知らなかった女の子、レイプなのにちょっと我慢していればすぐ済むからとごまかされてきた女の子、数えればキリがないが、ぼくは淳子もそんな類だと思っていたわけである。
ところが、撮影を始めてみると、事実はまったく逆。内容に引くどころか、カメラの前で脱糞するところから目がトローンとしてきた淳子。そのウンコを体中に塗りたくり、共演者から臭い女だ、ウンコ女だ、汚物女だと散々卑しめられているのに、淳子は怒ったり泣いたりするどころかかえって息を荒くして絶頂に達っしようとしていた。
こいつ変態じゃん! だまされて出演したのでも、頼まれて断り切れなくて出演したのでもなく、淳子は実はワクワクしながらこの現場に来ていたのだ。この撮影を機会に淳子の変態願望はドロドロと大量に彼女の外にあふれ出してきた。
尻まで見えるような超ミニをはいて街を歩き、しかもノーパンである。すっかりスカトロにはまって一人で浣腸オナニー。頭の中で何かがポーンと音を立てた。
普通はこんな女は色キ○ガイである。しかし、淳子の行為の中には彼女の意志がものすごく強くあったことをぼくは知っている。
世間にあることなどすべて「裏と表」である。ある人には価値のあることが、ある人にはまったく無価値であったり、ある人にきれいなものが、ある人にはきれいでない…なんてことは普通のことである。じゃ、エロなことに関しても同じじゃないだろうか。
その時になってぼくは淳子が最初の頃に言っていた言葉を理解した。親を離れてアパートを探していた淳子は、部屋を案内した若い不動産屋の男と何もないガラーンとした畳の上でセックスしたというのである。
「いい男でさ、やりたくなっちゃったんだよ」
きっと男は飲み屋あたりで仲間に自慢しているに違いない。バカな女がいて、簡単にやっちゃったよ。
でも、淳子はきっと反対にバカな男がいて簡単にできちゃったと考えているのだ。ぼくには淳子の方が絶対に主役の側だと思うんたけれど、どうだろう。男のバカっぽい常識の裏で女たちはクスクス笑っているような気がする。
さて、淳子と仕事をしたのはそれだけである。親しくなるのは淳子がモデル事務所をやめ、風俗の仕事をしたり、たまにフリーでAVの仕事をしているそんな頃だった。淳子は19歳になっていた。
ふと淳子のことを思い出したぼくは簡単な仕事の依頼があったので淳子に電話してみることにした。するとその電話は病院にかかっていたのだった。自室でシャワーを浴びていた時に突然意識がなくなり、危ないところだったという。低血糖による意識障害である。
そういえば、淳子が糖尿病だったなんてこの時初めて知った。まだ若い淳子だから不摂生の生活習慣病としての糖尿病ではなくて若年性の糖尿病。つまり本人には責任のない不幸な病気だが、糖尿病の恐ろしさはあまり知られていない。
血糖値をコントロールできなくなる若年性のこの病気では、インシュリン注射で血糖値のコントロールを厳密に行なわなければならない。しかし、そんなこと親からも離れ、いっしょに住む恋人や友達もいない彼女にはどだい無理なことだ。聞けばすでに何回も倒れているというではないか。救急車で運ばれたのは今回が初めてらしいが、淳子の場合すでに症状はずいぶん進行していて、腎臓の機能が激しく低下している上に、眼底の毛細血管がブドウ糖だらけの血液に長くさらされてきたためにすでに強い障害が出始めているという。
「私ね、もうすぐ失明するって言われたの」とベッドの中で少し寂しそうにつぶやいた淳子。
しかし、その5分後には今話した深刻なことなどまったく忘れて(本当に)、担当医が好みの男であること、そして、なんと急にザーメンが飲みたくなって、見舞い客の一人を誘って便所でフェラチオしたという話を嬉々として始めるのであった。
なんでこんなに刹那的なんだろう……。と初め思ったけれど、考えてみれば、こういうのは刹那的というのではなくて、彼女の心の中に時間の流れがないということなのではないだろうか。失明するかもしれないという恐怖と好みの医者がいたという喜びの感情の間がぶつ切れになっていて、まったくつながっていない。そんな風な心の流れはきっと彼女が生まれてから少しずつ少しずつできあがってきたものなのだろう。
来週退院するというので、車で迎えに行ってやることにした。初めて肌をふれあったのはその時だった。新宿の淳子のワンルーム・マンションにつれそい入ったところでキスをした。それはとっても自然な流れで、舌をからませて抱きしめると淳子はフルフルと小さく震えていた。
そして、ぼくはそのままそこにいついた。糖尿病の女と変態AV監督の奇妙な半同棲である。お互いに好きといっても、どちらかといえばインテリのぼくと中国の首都を知らないどころか一桁のカケ算も怪しい淳子のカップルである。仕事のない時は日がな何もしゃべることもなく、雑誌を見ながらゴロゴロしているだけの共同生活。
ところが、ある時淳子が自分を檻でペットのように飼ってほしいと言い出したのであった。